日本は教育水準の高い人材を育成に頼ってきましたが、時代の変化により改革が遅れ、世界のトレンドに遅れをとっています。
2の日本経済新聞(日経)は、「普遍的な大学教育による日本の高等教育」は日本人だけの「幻想」であり、日本はすでに先進国の中で「低等教育国」になりつつあると強調した。 。 文部科学省科学技術学術政策研究所のデータによると、日本の博士課程の学生数は、米国、英国、ドイツ、韓国に大きく遅れをとっている。 2018年には、日本で131人、韓国で290人が、100万人ごとに博士号を取得しました。
2007年には、米国の日本人卒業生の数も276人から117人に減少し、世界で21位にランクされました。 特に、中国を含む6か国の中で、10年前に比べて一人当たりの博士課程の学生数が減少しているのは日本だけです。
著名な科学文献数の国際ランキングでは、日本は1990年代まで世界で3位でしたが、いわゆる「失われた30年」を経て2018年には10位に落ち込みました。 同じ時期に、日本の産業競争力も後退した。 日経は、日本はイノベーションを推進する人材を育成できなかったため、構造的な弱点に問題があると指摘した。 主な原因は、大学院に比べて高等教育の必要性に対する社会的認識が低いことです。 企業の採用基準が学位のみである社会では、研究大学院の魅力を高めることはできないことを強調しておきます。
日経は、学業の過剰能力の問題と、学者よりも社会的経験を重視する一般的な雰囲気がこの傾向を後押ししていると考えています。
日本中央教育委員会の渡辺浩一郎会長は、「私たちの世代までは、大学を卒業したばかりなら大丈夫だったが、これからは違うだろう」と強調した。
日本はまた、専門的な研究者を育成するために武器を上げています。 その代表的な例が、早稲田大学を中心に、日本の公立・私立13大学が2018年から推進している「電力・エネルギー・専門能力開発プログラム」です。 目標は、学界や産業界の脱炭素化などのエネルギー分野に貢献できる博士課程のスタッフを養成することです。 各大学の卒業生や会社員が参加しています。
しかし、日経は、日本の現在の優先事項は、文部省などの政府の高等教育政策の責任者としての役割の欠如であり、企業が教育スタッフを雇うことはめったにないという事実を指摘した。より高い。 同紙は、教育と産業界が協力して長期的な視点で対応しない限り、現在の危機を回避することはできないと述べています。
[신윤재 기자][ⓒ 매일경제 & mk.co.kr, 무단전재 및 재배포 금지]
「音楽の魔術師。邪悪なポップカルチャーの恋人。謝罪のないクリエーター。いたるところにいる動物の友達。」





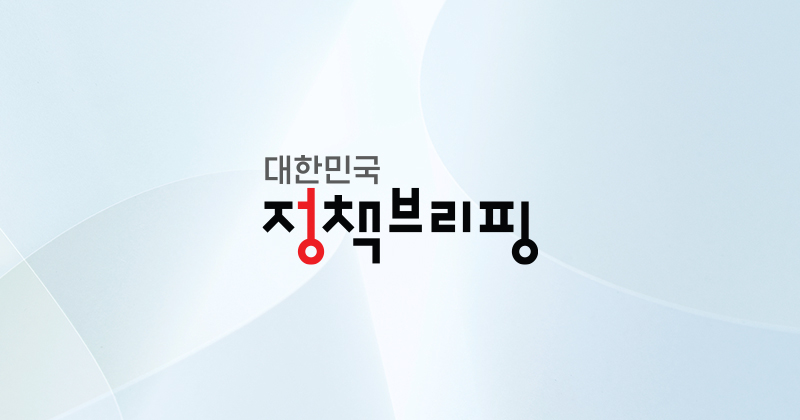

![[메뉴개발·전수] 名古屋「うな丼」商品化に向けた技術移転](http://www.foodnews.news/data/photos/20240625/art_17186020962783_a3aad9.png)