1999年2月、日本最大の通信会社であるNTTドコモがiModeを発表し、「スマートフォンメーカー」と見なされています。 また、携帯電話でインターネットを使用し、iAppと呼ばれるアプリマーケットプレイスからアプリをダウンロードするためのエコシステムも最初に導入しました。 2006年1月にiModが日本で非常に人気を博したため、NTTドコモは4,568万人の加入者を獲得し、世界最大のワイヤレスインターネットプロバイダーとしてギネスブックに登録されました。
しかし、それは世界市場をリードすることができませんでした。 これは、NTTドコモが自立を主張しすぎたためです。 iModを使用するには、NTTドメイン登録が不可欠でした。 すべてのアプリは社内で開発されています。
2007年にAppleがリリースしたiPhoneのビジネスモデルは、iModeとそれほど変わりませんでした。 違いは、世界中のユーザーが一緒にサービスを作成するオープンプラットフォーム戦略を採用していることです。 情報技術(IT)の専門家は、「NTTドコモの戦略が少し違っていたら、今日のアップルに代わって日本が世界的なITリーダーになっていただろう」と語っています。
1989年のNTTドコモの時価総額は1,639億ドル(約207兆ウォン)で、世界一にランクされています。 現在は987億ドルで、その約半分です。 Appleの時価総額は2.32兆ドルで、NTTDoCoMoの23.5倍です。
日本のビジネス界は、「日本はテクノロジーで勝ち、ビジネスで負ける」と言うことで自分自身を助けることがよくあります。 技術への自信過剰でオリジナリティを主張し、世界から遠ざかる日本の「ガラパゴス化」は、何十年にもわたって繰り返されてきました。
ソニーは性能面では優れた製品を示したものの、1975年にはビデオ、1992年には記録基準の競争に負けました。パフォーマンスと同じくらい低価格。
技術力だけを信じて、PCやスマートフォンの時代にタイムリーに対応できなかった日本のエレクトロニクス企業は、2000年代に崩壊しました。日本の自動車産業も、電気自動車への移行に遅れをとっていると見られています。ハイブリッド車や燃料電池車(FCV)などの独自技術。
「ガラパゴスジャパン」がおかしな進化を遂げたケースもあります。 日本のビール市場はその一例です。 2020年の日本のビール市場では、ビール風味の酒類「大山」のシェア(49%)が初めてオリジナルビール(38%)を上回りました。
市場シェアの逆転の背後には主流の傾向があります。 日本では、ビールの主成分である麦芽の量に比例した税金が課せられます。 大山は大豆とオレンジの皮で味付けされています。 その結果、2020年10月の最初の酒税見直し前は、ビールの酒税は77円でしたが、大山の酒税は28円でした。 大山の消費者物価はビールより90円安かった。
日本のビール会社は、その技術力を結集して、アルコール飲料を可能な限り安価にすることに注力してきました。 プレミアムビールの開発に注力した海外の競合他社のトレンドとは逆でした。 最後に、日本政府は、「酒税は日本ビールのガラパゴス諸島を誘発する」と指摘された後、2026年10月までにビール税を54.25円に統一することを決定した。
東京=ヨンヒョ特派員ジョンhugh@hankyung.com

「音楽の魔術師。邪悪なポップカルチャーの恋人。謝罪のないクリエーター。いたるところにいる動物の友達。」





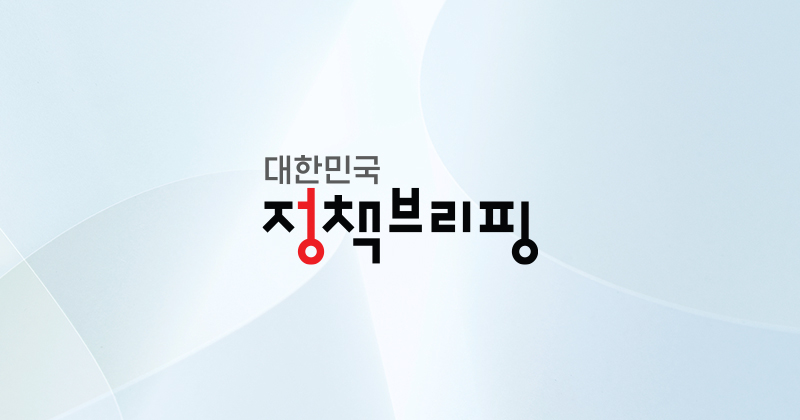

![[메뉴개발·전수] 名古屋「うな丼」商品化に向けた技術移転](http://www.foodnews.news/data/photos/20240625/art_17186020962783_a3aad9.png)