A. 豊かな国が「ノルブ・シンボ」だからです。
2015年にフランス・パリで開催された第21回気候変動条約締約国会議(COP21)にて、国連の潘基文事務総長(左から2番目)、フランスのローラン・ファビウス外相(中央)、フランソワ・オランド大統領(右から 2 番目) 最終的な合意、発表、拍手に署名します。 パリ/EPA 聯合ニュース

エジプトのシャルム・エル・シェイクで開催された国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の第27回締約国会議(COP27)が、閉幕後2日間、明け方まで交渉を重ね、20日に閉会した。 国際社会が気候変動による発展途上国に集中する「損失と損害」を支援するための基金を設立したことを除けば、収入はほとんどありませんでした。 さらに、この協定においても、誰が、どれだけ、何を、どのように支援するかについて当事者間で合意がなく、基金は「補償」や排出に対する法的責任を伴う「補償」ではなく、「支援」の性質のものでした。過去に先進国で温室効果ガスの排出量を削減したり、各国の政治家が見下したりしなくなったという批判があります。 気候変動に関する国連枠組条約は 1992 年に署名されました。しかし、30 年間、気候変動会議は毎年「強打」されてきました。 毎年各国の首脳が集まり、「地球を救う」と胸を躍らせていますが、合意したことさえきちんと実行されたことはありません。 どうして? 1つ目は、豊かな国のためです。 COPには多くの交渉グループが参加しています。 まず、欧州連合と、米国、日本、オーストラリアなどの非欧州先進国のグループであるアンブレラ グループがあります。 反対側には G77 グループの開発途上国があり、通常は中国と連携しています。 2000 年以来、韓国はスイスなどと環境保全グループ (GIE) を結成する交渉を行ってきました。 最も衝突するのは、「先進国対途上国」の交渉側です。 事実、締約国会議の 30 年の歴史は二国間の外交戦争であると言っても過言ではありません。 先進国とは、温室効果ガスの排出を削減するための「気候政策」を発明し、主導する国です。 欧州連合は、米国が属するアンブレラ グループよりも積極的なリーダーシップを示しています。 しかし、イーグル5兄弟のような地球の特殊部隊と考えると大間違い。 彼らは、「地球の危機」をチャンスと捉え、経済的利益を追求したい人々です。

ハンギョレインフォグラフィックチーム ※画像をクリックすると大きく表示されます。
たとえば、今年の締約国会議で、先進国は最終的に、発展途上国の要請に応じて損害賠償基金を作成することを「OK」しました。 それでも「代償でも代償でもない」と一線を画した。 彼らが補償または補償を認めた瞬間、彼らは支払わなければならない金額が天文学的に増加することを知っています. これが、締約国会議で合意が適切に達成されない理由です。 ペルーの農民が、ドイツの大手電力会社を相手に、彼の町の洪水防御費用を支払うよう訴えています。 昨年 8 月、気候変動チームは特集記事「世界は気候変動訴訟の最中にある」で取り上げました。 過去に温室効果ガスを排出して地球をここまで悪化させた先進国が、法的責任を負うと言った時点でおしまいだということを、彼らは十分承知している。 そのため、締約国会議の交渉において、先進国は気候変動に対する責任を決して認めません。 しかし、欧州連合のような先進国は、温室効果ガスの削減を主張していませんか? ナイーブです。 温室効果ガスの排出を削減するために、開発途上国は風力発電所で使用されるタービンを輸入し、さまざまな低炭素技術を導入する必要があります。 先進国にはその技術と資本があります。 彼らは、化石燃料システムから再生可能エネルギー システムへの移行プロセスにおいて、経済的な主導権を握ろうとしています。 アメリカはもっと問題です。 米国はさらに一歩進んで、開発途上国は先進国と同じ温室効果ガス削減義務を持つべきだと公然と主張しました。 実際、ブッシュ政権はこの理由で 2001 年に京都議定書からも脱退しました。 京都議定書は、先進国に対し、2008 年から 2012 年の間に温室効果ガス排出量を 1990 年の水準より 5.2% 削減することを約束しました。

2017 年 11 月、ペルーのアンデス山脈にある小さな町、ワラスに住む農家のサウル・ルチアーノ・リウヤ (写真右、後ろを振り返る) は、ハムのドイツ高等裁判所で裁判を待っています。 彼は、ドイツの電力会社 RWE に対して、彼の街の洪水防止費用の支払いを求めて訴訟を起こしています。 これは、先進国の過去の温室効果ガス排出に対する責任を法的に認めるかどうかを決定する歴史的なプロセスです。 ニュース Huaraz/EPA 聯合
韓国初の気候変動担当大使であるチョン・ネグォン元大使は、気候変動交渉が失敗し続ける理由のアルファとオメガとして米国を見ている。 そしてその根底にあるのが、1997年に米国上院で可決された「バド・ヘーゲル決議」です。決議には、「米国政府は、中国やインドなどの発展途上国の主要国が合意しない限り、気候条約の下でいかなる義務も負うべきではありません。 、米国からの同等の法的義務を受け入れないでください。」 米国を先頭に立つ先進国は、開発途上国に同様の削減義務を支持するよう求め、開発途上国は次のように答えました。 それはできない」「それなら先進国もできない」という話ですが、途上国から見れば、平等に削減義務を課すことに意味はあるのでしょうか。発展途上国からの怒りの声「安い化石燃料を使って経済を発展させ、発展途上国の植民地を演じてきた先進国ではないか」 第二に、気候変動へのパリ協定の制約により世界的な気候変動への対応が進んでいないことを指摘パリ協定は、世界の国々が力を合わせて「工業化に対する世界の気温上昇を1.5度以内に抑える」、それが難しい場合は「2度を大幅に下回るようにしよう」という内容です。米国の離脱などで京都議定書が難航したとき、世界は新たな約束をした。 契約に署名すると、参加者は抱き合って泣くと言われました。

ハンギョレインフォグラフィックチーム ※画像をクリックすると大きく表示されます。
パリ協定は、各国の「自主削減」を基本としています。 各国は、INDC (Intended Nationally Based Contribution) への参加を決定しました。 INDCですね…ちょっと難しいですね。 訳すと「各国の意思によって決まる貢献」という意味ですが、「貢献」という言葉はコミットメントや行動ではなく使われていることに注意が必要です。 強制と義務のようなものです。 I&Dとは、新聞記事で時々目にする「国家温室効果ガス削減目標(NDC)」のことです。 つまり、各国には、いつ、どの程度の GHG 削減目標があり、5 年ごとにパフォーマンス チェック、別名パリ協定が行われます。 これは、自主学習に似ています。 宿題を出し、自分で試験を受けるシステムです。 ちなみに、宿題をしないことで不利になる条項は契約書にありません。 宿題を自分でやらせて、強制がなかったらどうしますか? そもそも簡単なタスクを与える人とそうでない人がいるでしょう。 気候協定も例外ではありません。 温室効果ガスの削減量を低く設定している国と、削減目標を達成していない国があります。 一方、1992 年に合意された京都議定書は、先進国に対して具体的な削減を規定する強制的な合意でした。 もちろん、誰も持っていなかったので「バン」がありました。 チョン・ネグォン元大使は著書の中で、「気候変動交渉は、米国上院での単一のバド・ヘーゲル決議に対するユニークな世界的な戦いである」と要約しています。 冷静に考えましょう。 貧しい発展途上国は、気候変動に対する歴史的責任を負わず、経済的機会としてのみ利用しようとしているノルブ諸国に直面して、温室効果ガス排出量を「自発的に」削減するでしょうか? 気候変動交渉のもつれた糸を解くには、先進国、特に米国がまず変わらなければなりません。 途上国グループと共闘する中国を動かすには、米国が大きな譲歩を必要とする。 この点、今年の締約国会議で具体的な内容が示されていない「損失と損害」基金を設立するという提案は、先進国のレベルを示しているようで、頭が混乱します。 あぁ…地球に未来はあるの? 気候変動に詳しいナム・ジョンヨン記者fandg@hani.co.kr「チョム」

“Hardcore zombie fan. Incurable internet advocate. Subtly charming problem solver. Freelance Twitter ninja.”





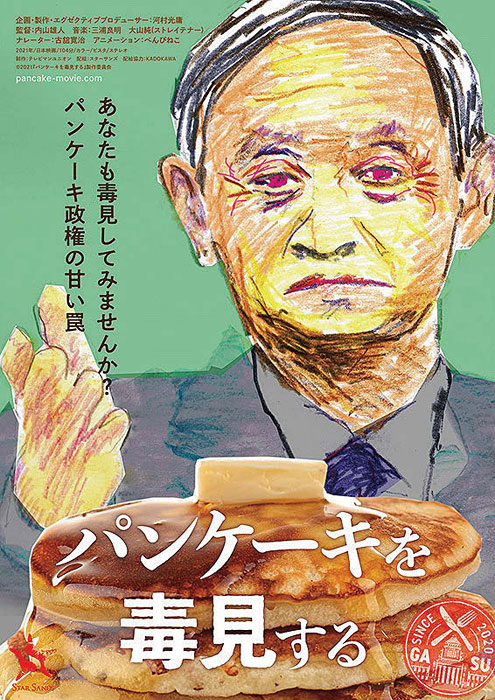
![[도쿄 30년, 일본 정치를 꿰뚫다] なぜ日本は再び安倍首相を選んだのか?](http://image.yes24.com/images/chyes24/5/1/5/b/515b9ffd5bc46a2c1eaa19f52c4d73c6.jpg)
