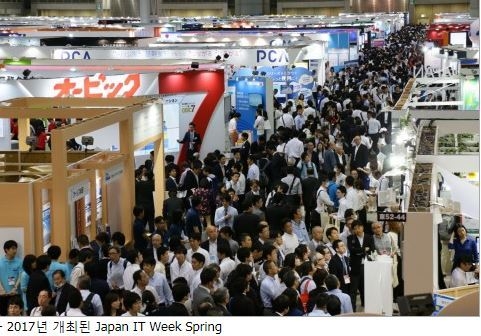|
| ▲23日、千葉県の神田外語大学で面接を終えて記念写真を撮っている神田外国語大学アジア語学科のリュ・ジェグァン教授。 |
韓国と日本の年金市場の専門家とされる神田外国語大学のリュ・ジェグァン教授(アジア語学科)は、デフォルト・オプション制度が日本の年金市場に与える影響についての質問に対し、次のように答えた。
リュ教授は、未来資産グループとサムスン生命保険に勤務し、韓国の老齢年金分野の専門研究者として長年活躍してきた。
私は現在、日本の神田外語大学アジア語学科で現代韓国経済学を学生に教えています。 主な研究分野は依然として老年学、老化に関する韓国と日本の比較、退職年金および個人年金制度です。
日本では2018年に企業型確定拠出年金(DC)にデフォルト・オプションが本格導入された。韓国より約5年早いが、日本ではデフォルト・オプションの大きな効果はなかったとみられる。
龍教授は日本のデフォルトオプションをどのように評価していますか? 23日、私は千葉県にある神田外国語大学の研究室で龍教授にお会いし、直接話を聞きました。
リュ教授は「結論から言えば、日本のデフォルトの選択肢は失敗だったと言える」とし、「韓国が代替教師として活用できる側面は十分にある」と付け加えた。
同氏はさらに、「結局、最大の問題は、日本のデフォルトオプションが施行されていないことだ」と強調し、「現在、DC型老齢年金を導入している企業のうち、デフォルトオプションを採用している企業の割合は、わずか40%です。」
この40%の企業のうち、元利保証商品をデフォルトした企業の割合は65%と高かった。
![[노후, K퇴직연금을 묻다 일본③] リュ・ジェグァン・神田外国語大学教授「元本と利息が保証された商品に依存すると、デフォルトオプションは失敗するだろう」](https://www.businesspost.co.kr/news/photo/202405/20240529164027_111645.jpg)
| ▲ 左の円グラフを見ると、DC年金会社のうちデフォルト・オプションを採用している企業の割合は2022年時点で39.1%にとどまっている。右のグラフを見ると、そのうち65.1%が元利担保型商品のデフォルトを起こしていることがわかる。 |
これは、年金資産を投資商品に振り向けることで収益を高め、老後資金に備えるというデフォルト・オプション制度導入の目的から大きく逸脱している。
一方、日本国民はDC型退職年金よりも投資型商品を選ぶことが多いようです。
日本企業年金(退職年金)協会によると、DC企業年金のうち投資型商品を選択する個人の割合は、2020年48.1%(3月下旬時点、以下同)から2021年は54.8%、2021年は57.9%と増加した。 2022 年と 2023 年。毎年 59.8% まで上昇し続けます。
結論として、デフォルトの選択肢を完全に企業の手に委ねることは逆効果でしかありません。
柳教授は「将来の老齢年金受給者の心情は投資型商品を望んでいるが、日本企業は将来損失が出た場合の批判を考慮してデフォルトオプションを安定的に使いすぎている」と述べた。 この問題を解決するには、「原則と利益に基づく商品を完全に排除する必要がある」と同氏は指摘した。
同氏はさらに、「この場合、企業や個人の手間が軽減され、デフォルトのオプションの目的そのものがうまく活用できるようになります。」と付け加えた。
![[노후, K퇴직연금을 묻다 일본③] リュ・ジェグァン・神田外国語大学教授「元本と利息が保証された商品に依存すると、デフォルトオプションは失敗するだろう」](https://www.businesspost.co.kr/news/photo/202405/20240529175711_144521.jpg)
| ▲日本のDC型老齢年金の商品割合の推移。 2023年には、デフォルト・オプションのある投資商品の割合はわずか33.5%でしたが、全DC商品に占める投資商品の割合は、2020年(48.1%)、2021年(54.8%)、2022年(57.9%)、および2022年(57.9%)では48.1%でした。 2023 年 (59.8%) と増加し続けます。 |
リュ教授はデフォルトオプション制度導入の効果を否定的に評価したが、日本の老齢年金市場全体の将来は明るいと考えた。
その根底には、若い世代を中心に投資文化が広がりつつあるという事実がある。
龍教授は、日本国民、特に若い世代の投資関心は今後も高まり続けると予測する。
これに関連して、龍教授は自身が行っている授業例も紹介した。
「ここは外国語大学なので、学生は一般的に経済学の科目を履修することに消極的です。 しかし、2022 年にここに着いたとき、私は基礎経済学と個人の資産管理を組み合わせたカンファレンスを設立しました。 1年目は80人が申し込み、2年目は120人、3年目は180人が申し込みました。 授業が終わった後も、基金とは何か、ローンとは何かという疑問を抱いている学生が多くいます。」
日本の老齢年金市場の大きな変化として、企業中心の確定給付型(DB)型から民営の直営型DC型への老齢年金市場の重心の移行が続いていることも挙げられている。
リュ教授は「人口構造の変化、資産運用環境の変化、低金利の継続により、政府や企業が老後の責任を負う時代から、個人が老後の備えをすべき時代へと認識が変わりつつある」と述べた。 「その結果、多くの企業がDB型からDC型に移行しつつある」と同氏は付け加えた。
![[노후, K퇴직연금을 묻다 일본③] リュ・ジェグァン・神田外国語大学教授「元本と利息が保証された商品に依存すると、デフォルトオプションは失敗するだろう」](https://www.businesspost.co.kr/news/photo/202405/20240529164624_175615.jpg)
| ▲ 神田外国語大学の喫茶店。 Ryu教授によると、最近、大学生の間で投資への関心が非常に高まっているという。 |
日本は5年ごとに年金財政力調査の結果を発表しており、今夏には新たな結果が公表される予定だ。 現在、日本の公的年金の所得代替率は60%程度だが、今年の発表では50%に低下すると予想されている。
リュ教授は「日本を含め公的年金の代替率は今後も低下していくことが予想されており、個人は公的年金よりも私的年金に注目するようになっている」と述べた。 「国が責任を持ち、企業が助ける」という古い考え方は日本でも同じです。」 「私たちが育ってきた福祉モデルは現在、個人に焦点を当てたものに移りつつあります」と彼は言う。
Ryu 教授は 1972 年 9 月生まれで、日本の中央大学で経済学の学士号、修士号、博士号を取得しています。
日韓文化交流基金招聘委員、未来資産退職研究所研究員、未来アセットマネジメント取締役、サムスン生命ライフファイナンス研究所主任研究員などを経て、現在に至る。 2022年4月より神田外語大学教授。
金融業界と民間研究機関での勤務経験をもとに、韓国と日本の社会経済の変化について詳しく研究しています。 特に、「社会経済変化による韓日比較研究」を主な研究テーマとしています。 エージング’。 ジャーナリスト キム・テヨン
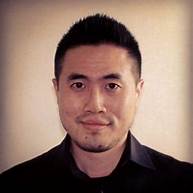
「テレビオタク。情熱的な料理のスペシャリスト。旅行の専門家。ウェブの第一人者。筋金入りのゾンビ好き。謝罪のない音楽狂信者。」

![[노후, K퇴직연금을 묻다 일본③] リュ・ジェグァン・神田外国語大学教授「元本と利息が保証された商品に依存すると、デフォルトオプションは失敗するだろう」](https://www.businesspost.co.kr/news/photo/202405/20240529163718_161357.jpg)