デイリー聯合(月刊、韓国紙) ホン・ジョンオ記者 | 20世紀初頭の大邱地域の変遷を日本人の目で観察・記録した日本の重要史料『大邱ムレオ』(嶺南大学出版局)が韓国語に翻訳されて出版された。
「大邱に聞く」は、1904年から1910年までの27年間、大邱に住んでいた日本人、河合朝夫の体験談を年代順に詳しく綴ったものです。
「大邱のマレー」は、大邱への日本人の定住の過程、純宗の南への旅、日本の皇太子の訪問など、当時の文化、事件と事件、および地域のインフラストラクチャを構築するプロセスを詳しく説明しています大邱で。 また、大邱の貿易と金融を司った日本人、大邱に派遣された司法・行政官僚についても詳しく紹介されています。 20世紀初頭の大邱の状況を確認できる韓国の文献が非常に少ない状況で、当時の大邱の有力な官民の姿とその変遷を詳しく知ることができる貴重な資料として評価されている.
「大邱の水」の代表翻訳者である嶺南大学人文科学研究所のユン・ギョンエ研究教授は、「現存する翻訳書には原文がほとんどなく、歴史資料などの重要人物の名前がほとんど残っていない」と話した。翻訳されていないので、日本語を知らない研究者にとっては非常に残念です. 今回、嶺南大学が出版した大邱の魚は、その失望の多くを補った. うまく活用できます。 “
この「大邱水」翻訳プロジェクトは、2021年嶺南大学LINC+プロジェクトグループ(現LINC3.0プロジェクトグループ)の就職能力強化プログラムの一環として行われました。 具体的には、このプロジェクトには、YU で日本語と日本文学を専攻した 12 人の学部生と大学院生 (チョン チャンヒ、キム ソジン、キム ユヨン、ソン キフン、シム ヨンジェ、オ チャンヒ、イ スミン、リム ドンヨン、チョン ミンジ、チョン スヒョン、山下青葉)、吉村遥)が担当することで注目を集めている。 これらの学生は、約 8 か月間、翻訳から校正、編集まで、出版プロセス全体に直接参加しました。 「大邱の水」の出版を皮切りに、翻訳チームは、現代の大邱と慶尚北道の重要な日本語資料を年に 1 冊、一貫して翻訳し、出版する予定です。 2022年度のプロジェクトとして、1920年代の大邱の朝鮮社会を記録した文書の翻訳をすでに完了しており、編集作業後まもなく嶺南大学出版局から出版される予定です。
嶺南大学国語国文学科の崔範順(チェ・ボムスン)学科長は、「現地の重要な史料が、現地の大学で関連分野を専攻する学生たちによって日本語に直接翻訳され、出版されたことは非常に重要だ。 嶺南大学校国語国文学科は、大邱・慶北での近代史翻訳事業をもとに、地域社会に貢献し、学生のコアスキルを強化できる活動を継続していきます。

“Hardcore zombie fan. Incurable internet advocate. Subtly charming problem solver. Freelance Twitter ninja.”





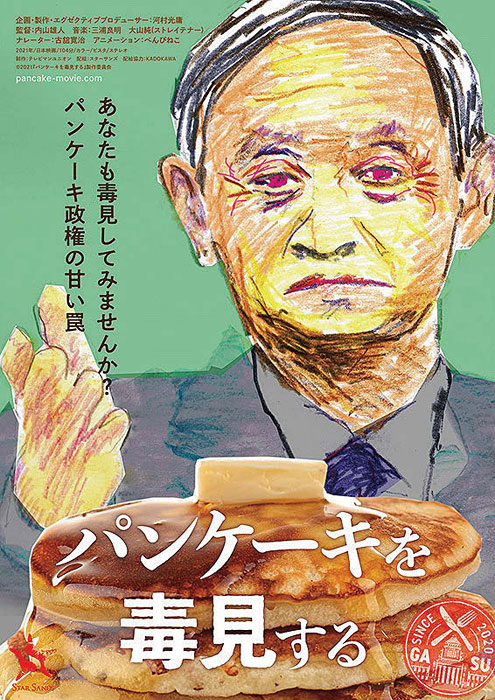
![[도쿄 30년, 일본 정치를 꿰뚫다] なぜ日本は再び安倍首相を選んだのか?](http://image.yes24.com/images/chyes24/5/1/5/b/515b9ffd5bc46a2c1eaa19f52c4d73c6.jpg)
