動揺する日本(2)アベノミクスの余波
会社の成長 → 期待に沿わなかった昇給
「安倍政権は国民のカネを盗み、会社準備金を積み上げた」
107兆円超予算の3分の2は生活保護と借金返済額
「円」に酔い、構造改革の欠如。 小さなカート、部門、支部を除く空のカート
2012 年 12 月 26 日に日本で最も長く首相を務めた安倍晋三元首相が就任したとき、日経 225 指数は 10,395 でした。 2019 年 9 月 15 日の時点で、退職日指数は 23,656 でした。 在任中の上昇率は230%で歴代首相の中で3番目に高い。
失業率は 4.3% から 2.2% に低下しました。 アベノミクスという大規模な景気刺激策が、20年にわたる不況に見舞われた日本経済を活性化させたと評価されているのはこのためだ。
アベノミクスは、大規模な金融緩和、積極的な財政政策、大胆な成長戦略の「3 本の矢」で構成されています。 三本の矢が当たって会社の業績が上がれば、設備投資や賃金の上昇、所得や分配の増加による消費の増加につながるという考えでした。
◆ 収益が上がっても設備投資や賃上げは無視
企業業績を上げる代表的な手段は、円安を誘導することでした。 発足当時85.35円だった円は、2015年6月には125.21円まで下落した。法人税率は2014年の34.62%から2018年には29.74%に引き下げられ、企業の負担が軽減された。 その代わり、消費税を二度引き上げて税収を増やした。
ただし、純利益の増加を構造投資や賃上げに使用する代わりに、会社はそれを準備金に変えました。 2012年に304兆円(約2929兆ウォン)だった企業準備金は、2018年には463兆円と1.5倍に増加した.設備投資の伸び率は2000年代の4.2%を下回り、3%にとどまった.彼も消極的だった.仕事について。 人件費を削減するために、文書化されていない労働者の数が増えました。
その結果、期待されていた賃金、所得、消費の増加は見られませんでした。 2012 年末に -1.9% だった実質賃金の伸び率は、2019 年末には -1.1% でした。
![日本政府は経済政策の失敗と実践を30年間繰り返す [정영효의 일본산업 분석]](https://img.hankyung.com/photo/202204/01.29718350.1.jpg)
企業利益に占める人件費の割合である労働の割合は、72% から 66% に低下しました。 アベノミクスの 8 年間で、名目国内総生産 (GDP) は 492 兆円から 505 兆円に変化しませんでした。
駒沢大学名誉教授の小栗隆氏は「安倍政権は国民から金を盗み、企業の準備金を積み上げてきた」と語った。
安倍総理大臣の辞任から3年目の2022年、日本経済はアベノミクスの後遺症に苦しんでいます。 金融緩和や財政拡大政策への過度の依存、規制改革や成長分野への投資不足により、経済のファンダメンタルズは弱体化しています。 日本の潜在成長率は、2005年に1%ラインを突破して以来、20年近く0%台で推移しています。
第一生命経済研究所の永浜敏宏チーフエコノミストは毎日新聞の取材に対し、「生産性を左右する労働市場の改革は、解雇規制の根幹に触れていない」と語った。
日本政府がパッチワークと実技を30年繰り返す
安倍政権だけが構造改革を無視し、いじくり回して日本経済を弱体化させているわけではない。 横浜市立大学のグク・ジョンホ教授は、日本の「失われた30年」の長期不況を「政策の誤りと閉鎖によって失われた30年間の成長」と呼んだ。
彼が指摘したように、日本政府と与党自民党の経済政策における失敗と実践は 30 年間繰り返されてきた。 日本経済が1956年から1973年にかけて年平均9.1%の成長を続ける中、日本政府は1973年を「福祉元年」と定め、大規模な社会保障制度を創設しました。
しかし、1973年は高度成長期が終わった年でもありました。 この時代に作られた巨大な社会保障制度は、常に日本の足首を支えています。
![日本政府は経済政策の失敗と実践を30年間繰り返す [정영효의 일본산업 분석]](https://img.hankyung.com/photo/202204/01.29718351.1.jpg)
今年の日本の予算は107兆5,964億円で、10年連続で過去最高を記録した。 毎年、予算の約 3 割が赤字国債の発行で占められています。 少子高齢化で税収が不足しているからだ。 今年度予算は、社会保障設備費(36兆円)と国債償還費(24兆円)だけで予算全体の3分の2を占める。 これが、日本政府が新しい成長戦略に予算を集中させることが難しい理由です。
ゴールドマン・サックスの元アナリストであり、菅義偉元首相の「経済の頭脳」であるデビッド・アトキンソン氏は、「1000兆円以上の借金を抱える国は、大規模な災害に見舞われれば、立ち直ることはできないだろう」と警告した。規模の災害. 地震のように ».
◆チーフの名物は食べない
デフレ脱却という日本政府の目標は間違っているとの指摘もある。 野村総合研究所のチーフエコノミストである木内隆英氏は、「日本経済の崩壊はインフレによるものではなく、潜在力の欠如によるものだ」と述べた。
素材、部品、設備の生産を中心とした経済構造を変えることを怠っていると批判されている。 日本のものづくりの強みは、信頼性の高い製品を量産する技術です。 しかし、単純なデジタル製品の時代にデジタル製品の構造が変化し、日本の長年の精密加工技術を使用する余地が少なくなりました。 労働生産性は主要国の底辺にぶら下がっており、低価格で適度な品質を提供する中国と競争するために値下げに苦労している。
アップルのようなビッグテクノロジーの出現により米国経済が軌道に乗りつつある一方で、日本の時価総額上位の銘柄は依然としてインフラストラクチャー企業でいっぱいです。 日本生産性本部の木内康宏主任研究員は「1990年代は仕事の効率化が付加価値につながったが、今はコスト削減が値下げの源泉になっている」と指摘する。
東京=ヨンヒョ特派員 チョン・ヒューグ@hankyung.com

「音楽の魔術師。邪悪なポップカルチャーの恋人。謝罪のないクリエーター。いたるところにいる動物の友達。」

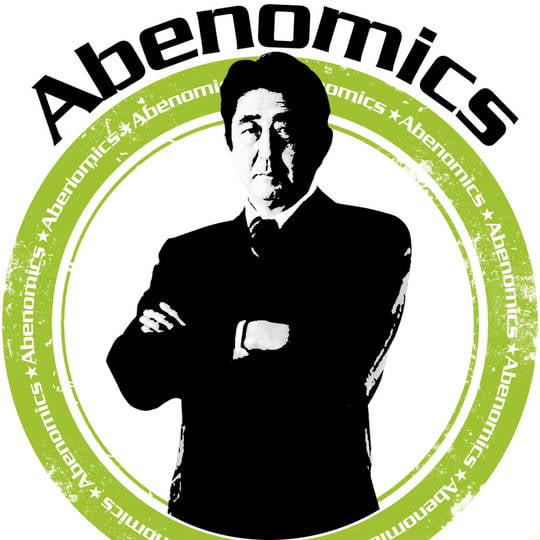



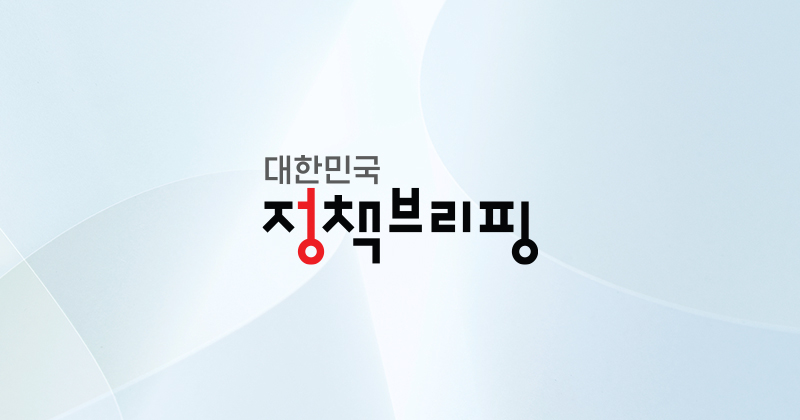

![[메뉴개발·전수] 名古屋「うな丼」商品化に向けた技術移転](http://www.foodnews.news/data/photos/20240625/art_17186020962783_a3aad9.png)