政党の指名を除くが、最終的には政治的志向に基づく投票
先進国でも、直接制度と予約制度には多くの違いがあります。
1日に行われた第8回全国教育監督選挙は、有権者の無関心で「点滅」する選挙で行われたことが指摘されており、教育監督の直接制度に代わるものが注目されている。 。
5日の全国選挙管理委員会によると、今回の教育監督選挙では、市長・知事選挙の無効票数(35,928票)の2.6倍に相当する93,227票の無効票が得られた。
これは、有権者が監督者の選挙にそれほど関心がないことを示しています。
特に、政治的に中立であるはずの総選挙がイデオロギー的な対立となり、個人攻撃が多発していることから、制度の変更や改善を求める声が続いている。
◇大統領指名制度→丸太制度→直接選挙制度…政治的対立へと変貌
教育監督は1991年まで大統領によって任命され、1991年から2006年まで教育委員会または選挙区によって選出された。
直接制度は、教育監督者の選挙への住民の参加を確保するために2007年に導入されました。
監督者としての現在の選挙では、政党は選挙に参加できず、監督官庁の候補者は特定の政党を支持または反対することはできません。
しかし、教育監督者の選挙は、実際には進歩主義者と保守派の政治的対立として行われ、政党制に基づく地方政府の首長選挙ではなく、政治的対立として行われた。
一部のアナリストは、監督候補者への関心が低いため、候補者の政治的約束ではなく、分野やイデオロギーに従って投票するしかないと言います。
ダンクック大学政治学国際関係学部のキム・ヨンジン博士とサンジュン・サン教授が書いた論文「監督選挙の特徴の分析:候補者、イデオロギー、選挙人、政党」によるとDankook大学の政治学および国際関係学部では、2018年の最後の地方選挙での監督者の選挙のために、合計1,000人の有権者にインタビューが行われました。政治への関心が高いほど、投票への参加も多くなります。監督の選挙。
「首相選挙への有権者の関心と参加が低かったため、首相選挙は候補者や政治ではなく、政治的要因や状況によって一掃された」と研究者らは分析した。
地方自治体の長と教育長が異なる政治的傾向を持っている場合、予算をめぐる対立などがしばしば発生します。
◇州の市長・知事指名制度やランニングメイト制度などの代替案
教育監督者の直接制度に代わるものとして、「市と州の知事を任命する制度」、「コンパニオン型の直接居住制度」、「限定直接居住制度」が提案された。
市長・知事指名制度とは、市・県議会が教育長候補を推薦し、市長・知事が検証を経てその中から長官を選任する制度です。
地方自治体の長が教育長を任命すれば、地方自治体の長と教育長との対立の可能性が減るというメリットがあります。
しかし、コインの両面のように、監督候補者は地方自治体の指導者のために並んでいます。
また、「地方自治」と住民の参加を保証するという直接制度の本来の目的とは対照的に、決定的な制限もあります。
ランニングメイト型の直接居住者選挙制度は、米国の大統領と副大統領のように、市長/州知事と教育監督官の候補者が一緒に走る形式です。
利点は、指名段階から監督の候補者を選択できるため、有権者が事前に候補者を評価し、州の市長/知事と監督の間の対立を減らすことができることです。
しかし、政党のある市長・知事と政党のない教育監督者が立候補すると、教育の中立性が損なわれるという問題があります。
光州教育大学のパク・ナムキ教授は、「ランニングメイト制度を導入する場合、州長・知事とはランニングメイトの決定方法を変えるべきだ」と強調した。
中立が必要だが、実際に政治的対立が避けられないのであれば、有権者が政治の方向性を明確に理解できるように、教育監督も党の指名を受けるべきだと主張する人もいる。
監督者の選挙には、保護者、学校職員、事務職員、私立学校の役員など、教育関係者のみが参加する限定的な直接選挙制度が提案されている。
教育に大きな関心や理解を持っている人が監督を選出するのは有利だと思うが、地方自治体の教育費を払っている住民全員が選挙に参加できないわけではないので、物議をかもしている。
監督者の直接制度の代替案にも明らかな長所と短所があるため、より大きな枠組みで制度を改革するのではなく、直接制度の問題を解決する方法を模索する必要があるとの意見もある。
淑明女子大学教育学部のソン・キチャン教授は、「直接の監督制度は最善ではないが、別の制度に切り替えても改善される可能性は低い。改善が必要だ」と述べた。
監督選挙の有権者の年齢を大幅に下げて、政策立案者が政治の影響力を持つ人々によって直接選出され、それによって関連性と関心が高まるべきだと主張する人もいます。
パク・ナムギ教授は「投票年齢を下げる必要がある」と述べた。 「別の方法は、14歳からの子供たちに投票を許可して、彼らが自分の約束を発展させ、候補者の約束の妥当性を判断する機会を持てるようにすることです。」
この見方には賛否両論があるかもしれません。
選挙権が18歳にまで拡大されたときでさえ、教室の政治化と学習権の侵害に起因する対立に基づいて多くの反対意見がありました。
正義党の政治委員であるソン・ギョンウォン氏は、「直接選挙制度に代わるものは、監督の政治的中立性を規定する憲法を変更しない限りない」と述べた。

◇先進国も「違う」…アメリカの14州での直接制ドイツとフランスの交際制
一部の先進国では、教育の監督者が任命され、場合によっては、人々が直接監督者を選出します。
米国の場合、州ごとに監督者の選出方法が異なり、25州では州知事が監督官を任命し、11州では州知事が監督官を任命します。
住民が直接監督を選出する14州のうち、8州が監督党の任命を認め、残りの6州は党なしで運営されなければならない。
日本では、韓国教育委員会の代わりに教育委員会が教育委員会を設置しており、教育委員会のメンバーは地方議会の同意を得て地方組織の長によって任命されています。
韓国の教育監督は、教育委員会の委員の中から教育委員会によって任命されています。
ドイツでは、州ごとに教育省と教育大臣があり、州ごとに異なる教育行政システムがあります。
州知事は州教育大臣を任命し、州教育大臣は州教育監督官を任命します。
フランスでは、教育監督者は大統領によって任命され、議会の承認プロセスはありません。
地方議会は監督者の教育力を制限することはできません。
/ユンハプニュース

“Hardcore zombie fan. Incurable internet advocate. Subtly charming problem solver. Freelance Twitter ninja.”





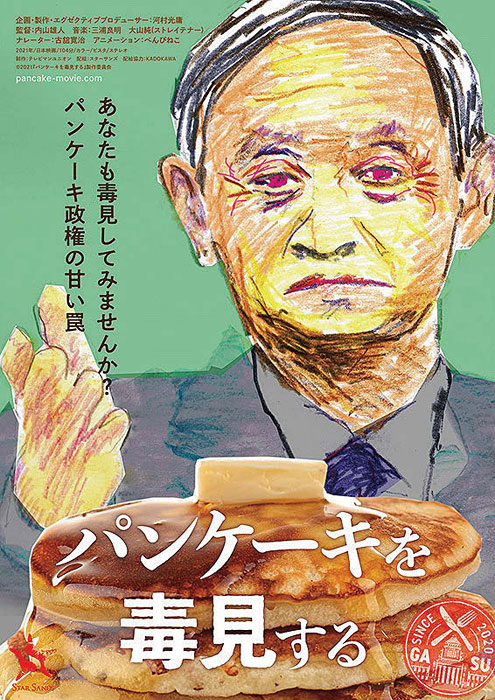
![[도쿄 30년, 일본 정치를 꿰뚫다] なぜ日本は再び安倍首相を選んだのか?](http://image.yes24.com/images/chyes24/5/1/5/b/515b9ffd5bc46a2c1eaa19f52c4d73c6.jpg)
