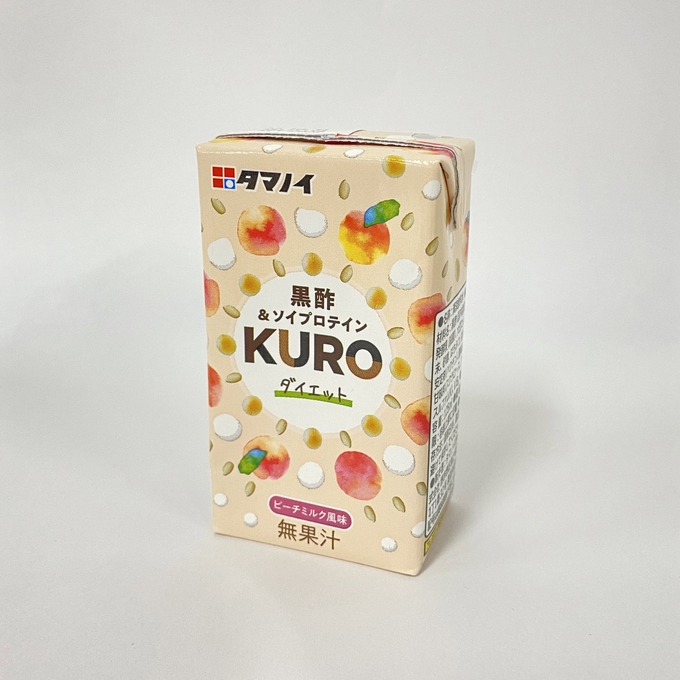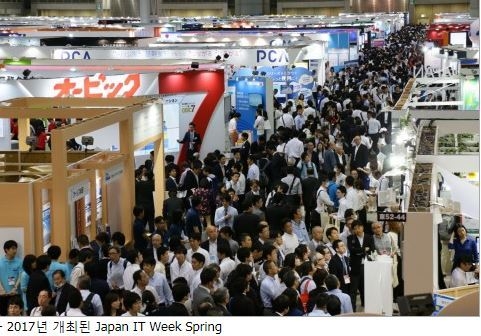日本では、長期的な美と機能の向上を目指して、酢飲料を求める消費者が増えています。 東京支社によると、日本の家庭用酢市場における飲用酢市場の規模は、2020年に料理用に289億円、つまり294億円を超え、市場に変化が生じた。
日本での酢の飲み方は、2010年からフルーツビネガーが人気を博し、2017年には韓国製品「ミチョ」とミツカン(日本の代表的な酢会社)がマーケットリーダーの「フルティス」を発売しました。
特にフルーツビネガーは甘くて飲みやすいことから人気があり、2017年以降消費量が急増しています。2021年上半期には市場規模が312億円に拡大し、飲み物は255億円から飲酒になりました。生酢57億円。
主に料理に使用される穀物酢は、2020年に147,800 klに減少し、2019年から11%減少しました。特に穀物酢は寿司に広く使用されていますが、COVIDにより外食の需要が減少しています。 -19の発生。
オンライン調査会社のMyVoicecomInc.が実施した調査結果によると、酢を飲む人に期待される効果の40.5%が「倦怠感」が最も高く、「健康維持」「血液の改善」がそれに続いた。 。
酢の選択では、「味」が67.5%、「飲みやすい」、「価格」がそれぞれ40%、「原材料」、「効果/効能」、「成分/添加物」がそれぞれ約20%でした。回答者の約33%が将来酢を飲みたいと答えました。
CJジャパンのミチョシリーズは、その利便性と実用性により、飲料酢の年間売上高が100億円を超えました。 消化、新陳代謝、脂肪の減少などの美容効果が期待できることを強調することで、彼女は美容消費者から良い反応を得ています。
日本の調味料会社である玉の井町が3月に発売した黒酢と大豆たんぱく質のKUROは、コロナウイルス以降の消費者の健康意識を考慮して作られました。 ピーチミルクと高アミノ酸黒酢を組み合わせて甘みを高めています。 また、健康飲料のイメージを強調するために植物性タンパク質を添加しています。
酢メーカーのまるかんちょうも、玄米100%、ふじりんご、ワイルドブルーベリー、紀州南小梅の3種類の「黒酢を飲むシリーズ」を発売しました。
一方、東京・幕張メッセで開催された「東京フードエキスポ2021(Foodex Japan)」では、3月9日から12日までの4日間、K-Functionalフードプロモーションセンターを運営しました。 期間中、PRルームで韓国の酢を飲む試飲会が開催され、血中トリグリセリドの増加と食後の内臓脂肪の減少の関数として記録され、消費者や地元のバイヤーから好評を博しました。 。
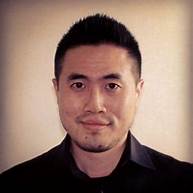
「テレビオタク。情熱的な料理のスペシャリスト。旅行の専門家。ウェブの第一人者。筋金入りのゾンビ好き。謝罪のない音楽狂信者。」

![[지금 일본은] 美容と健康のために酢を飲む日本の消費者](http://www.foodnews.news/data/photos/20220624/art_16552544790141_a4d3cd.png)