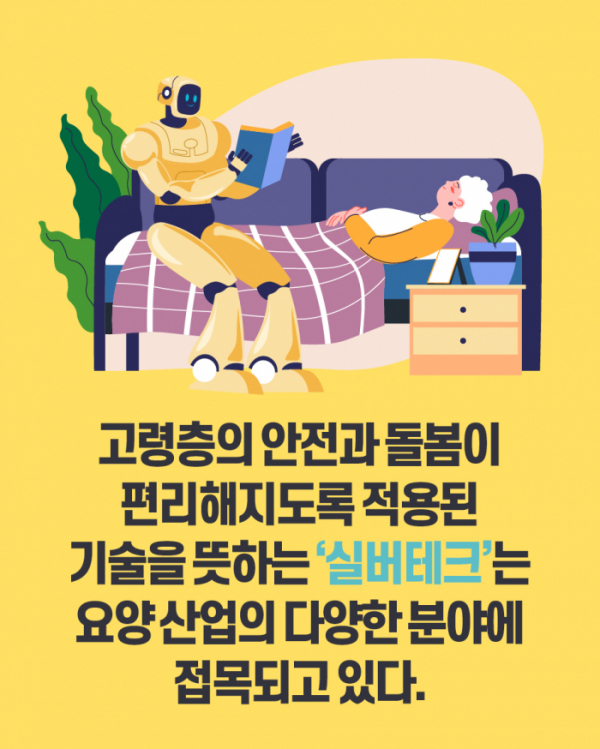

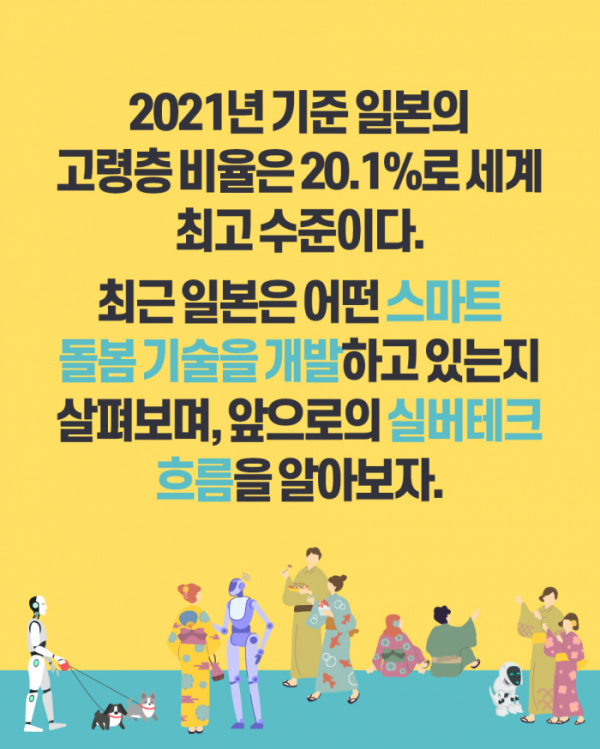
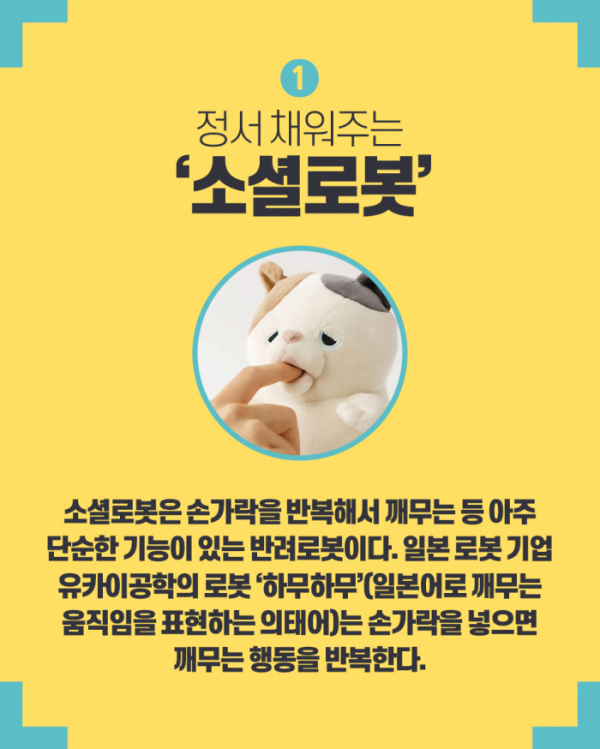
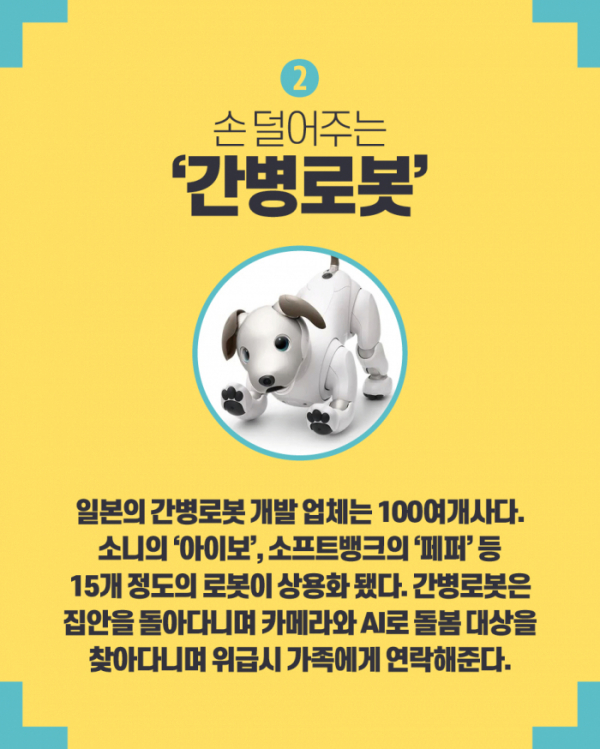
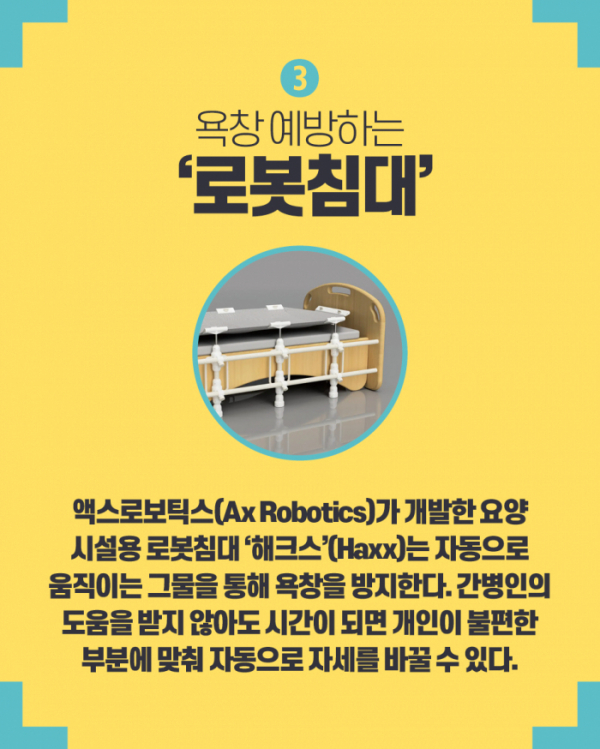
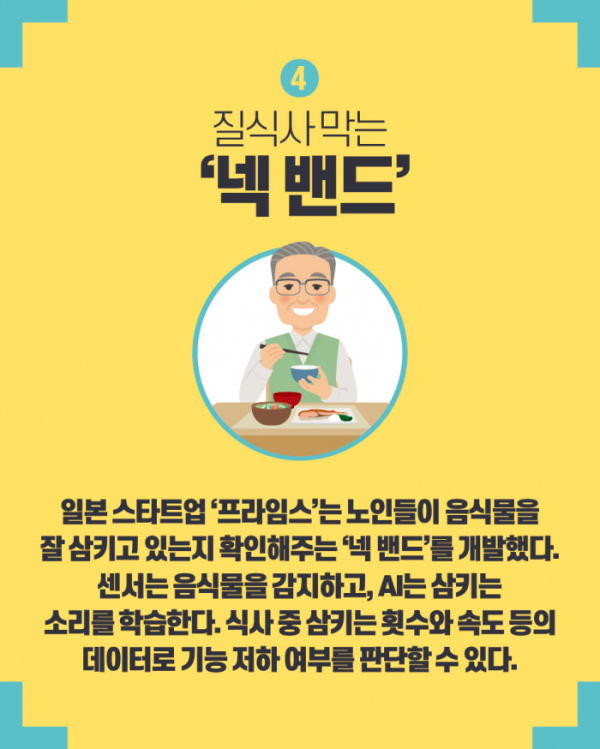
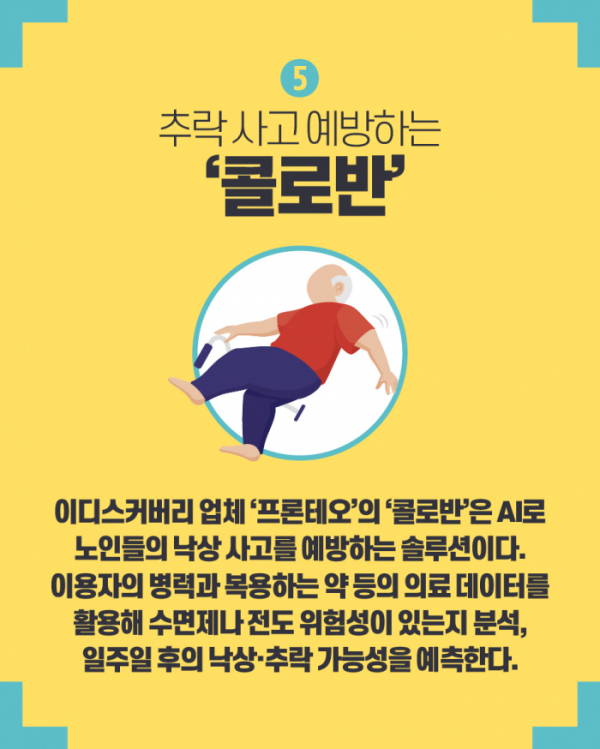
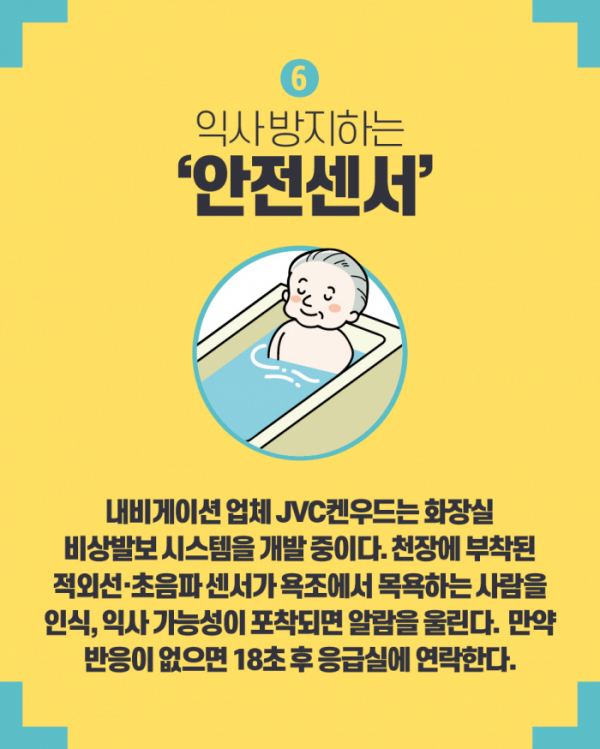
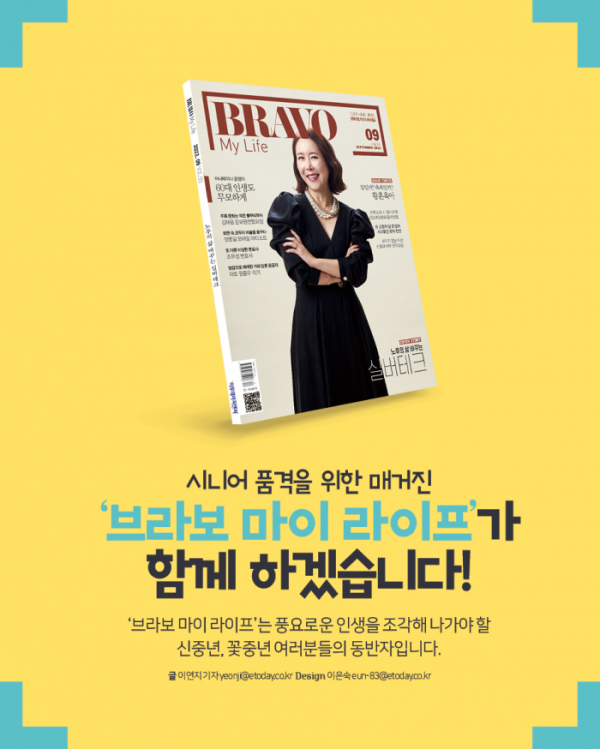
「シルバーテック」とは、高齢者の安全と介護を容易にする技術を指し、介護業界のさまざまな分野に応用されています。 人工知能によるリアルタイム監視、IoTによる身近な支援、ビッグデータ分析によるパーソナライズされた支援サービスが代表例です。
2021年、日本の高齢者比率は20.1%で世界一。 少子高齢化が先駆け、2000年代から「先進トイレ」「臥床」「介護ロボット」などの技術開発が進んでいますが、その支援技術の種類を見てみましょう。最近開発されており、銀技術の未来を発見しています。
1. 感情を満たしてくれる「ソーシャルロボット」
ソーシャル ロボットは、くすぐられると笑う、指を何度も噛むなどの非常に単純な機能を持つコンパニオン ロボットです。 日本のロボット会社、ユカイ工学の「Qoobo」は、丸いクッションに尻尾が付いたロボットです。 顔はありませんが、動物のように尻尾を振るレスポンシブテクノロジーを備えています。 世界家電展示会「CES 2022」に出展されたロボット「はむはむ」は、指を入れると噛む動作を繰り返す。 これは、高次機能ではなく、単純な反復行動が感情を助けることができることを示す事例です。
2. 労力を軽減する「介護ロボット」
高齢化率が最も高い日本では、介護人材の不足が大きな問題となっています。 この問題を解決するために最も開発されたのが介護ロボットです。 介護ロボットの開発企業は約100社あり、これまでに約15台のロボットが製品化されています。 ソニーの「aibo」やソフトバンクの「Pepper」が代表例。 aiboは介護者に入り、カメラと人工知能を持った介護者を探すために家中を動き回ります。 高齢者が自宅で一人で倒れた場合、写真を撮って家族に送ることができ、すぐに救急車を呼ぶことができます。
3. 床ずれを防ぐ「ロボットベッド」
Ax Roboticsが開発した介護施設向けロボットベッド「Haxx」は、自動で動くメッシュで床ずれを防ぎ、個人に合わせて姿勢を正すことができます。 褥瘡を予防するには、2 時間ごとに姿勢を変える必要があり、これには介護者の多大な労力が必要です。 ロボットベッドは、時間に応じてユーザーの姿勢を自動的に変更します。 今後は、排泄物検知や生体情報計測などの技術も予定されています。
4.窒息を防ぐ「ストラップ」
日本のスタートアップであるプライムズは、高齢者が食べ物をうまく飲み込んでいるかどうかをチェックする「首輪」を開発しました。 加齢に伴って食べ物を飲み込む機能が低下すると、誤嚥性肺炎や窒息の危険性があります。 ネックバンドに搭載されたセンサーが食べ物がうまく食べられているかを検知し、AIが飲み込む音を学習。 食事中の嚥下の回数や速度などのデータを収集して、機能が損なわれているかどうかを判断できます。
5. 転落事故を防ぐ「コロバン」
eディスカバリー企業「Fronteo」の「Colovan」は、高齢者がAI事故に巻き込まれないようにするソリューションです。 ユーザーの病歴や服薬などの医療データを用いて、睡眠薬や転倒リスクの有無を分析し、1週間後の転倒や転倒の可能性を予測。 この数値に基づいて、車椅子の使用を推奨することができます。 Colovan を使用している病院は、ソリューションの導入後、ドロップ率が 3 分の 2 減少したと報告しています。
6.溺れるのを防ぐ「センサー」
高齢者の溺水事故の90%は自宅の浴槽で発生しています。 一人暮らしの家庭では、事故が起きても発見が遅れることが多い。 また、洗濯中に事故が発生すると、急激な温度変化による心臓発作の可能性が高まります。 ナビゲーション会社の JVC ケンウッドは、トイレの緊急通報システムを開発しています。 天井に取り付けられた赤外線と超音波のセンサーが浴槽に入浴している人を認識し、溺れる可能性がある場合に警報を発します。 アラームに反応がない場合、18秒後に自動的に救急車を呼ぶシステムです。

「音楽の魔術師。邪悪なポップカルチャーの恋人。謝罪のないクリエーター。いたるところにいる動物の友達。」

![[카드뉴스] スマートケアがシルバーテクノロジーに飛躍 – Bravo My Life](https://img.etoday.co.kr/pto_db/2022/09/600/20220913095150_1796356_945_626.jpg)



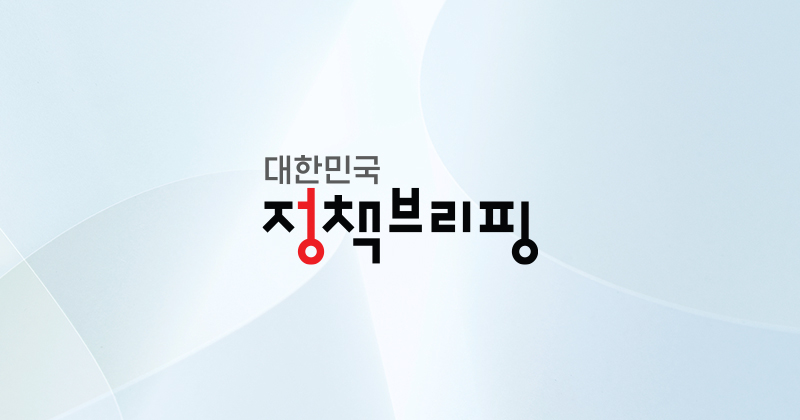

![[메뉴개발·전수] 名古屋「うな丼」商品化に向けた技術移転](http://www.foodnews.news/data/photos/20240625/art_17186020962783_a3aad9.png)