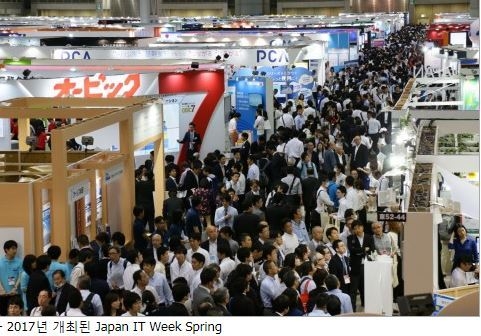イラストパク・チョヒ記者 choky@donga.com
泉 治治(いずみ じはる) 日本出身、ソクキョン大学グローバルビジネス言語学部教授
京畿道果川市にある中史博物館の開館10周年を記念して特別展「藤津川蘭学」が開催される。 展覧会初日の今月3日、展示を見に行ってきました。
韓国の文化芸術に興味があり、25歳で韓国に留学に来ましたが、どうしても近づきがたい人がいました。 チュサ・キム・ジョンヒ先生。 隙のない字のようで、勉強も大変なので、あえて近づきませんでした。
きっかけは、2020年11月から韓国国立中央博物館で開催された中史「世ハンド」特別展でした。 展覧会では、中左の研究者、中左を知る学者として日本人の藤塚鄰(ふじつか・ちかし、1879-1948)が紹介されました。 京城帝国大学の教授として、1936年に中史金正煕の研究で最初に博士号を取得した学者であり、1932年頃から1944年まで「世漢堂」のオーナーでもあった。
最初は中佐と日本人とどんな関係があるのかと思ったが、調べてみて驚いた。 大切な人がいなくて寂しい…。 しかし、藤塚のことを知らなかったのは私だけではなかった。 その時、私は国立中央博物館で外国人記者の前で藤塚についてプレゼンテーションをする機会を与えられた。 私が中佐と親しくなったのは、藤塚さんと出会ったのと同じ60歳になってからでした。
藤塚は1940年に京城帝国大学を退職すると、『青ハンド』を持って日本に帰国したが、それを韓国に返却した。 父の遺志を受けて、果川市で父が収集した中氏の書道26点と中氏関連の書画約70点など約1万点の資料を寄贈した。 2013 年に中佐博物館が開館するにあたり、秋直氏の寄付に多大な貢献があり、同博物館はその後 10 年間にわたり着実に学術的成果を上げてきました。
この「藤津川七鶴」では、藤塚から寄贈された遺品のうち、江戸時代(1603年~1868年)の藤塚の生涯と七鶴を通じた学問、および藤塚家の資料を調べることができます。 「南学」とは、江戸時代にオランダから長崎を経由して日本に伝わった西洋医学や科学知識のことです。 学業成績を証明した。
特に興味を持ったのは、大学時代にレポートとして発表した「適度な勉強」であり、卒業論文も適度な勉強だったということです。 当時としては先進的な歴史研究の方法論で臨んだとはいえ、彼に与えた影響は大きかったに違いない。 藤塚家で教えられた国学資料、思想に影響を与えた中庸、生涯研究した思想対話、そして清朝と日本の学者に認められ東洋に学術交流の波を巻き起こした中佐の研究アジア。 この展示を通して藤塚の深い思想や人間像を垣間見ることができ、藤塚が中左に共感していたことがよく分かりました。 少しずつ中佐に近づいていってよかったです。
また、6日にはチュサ博物館と韓国国立博物館をオンラインで結び、在仙台日本総領事館と東北学院が共催し、チュサと藤塚を通じて21世紀の韓日友好を促進する。 「友好交流」に関するセミナー。 中佐博物館と中佐研究が世界的に注目されていることを実感する時となった。
そんな中、2021年2月に2匹の猫が我が家に引き取られました。 そのうちの1つは、チュサの代表的な蘭の絵「ブリソンランド」にちなんで「ブリ」と名付けられました。 私が近づくと避けてしまうのですが、時々無意識に近寄ってきて体をさすって消えてしまうことがあります。 いわゆる「ツンデレ猫」ですが、難解な魅力を持った我が家の「小さなチューサ」です。
中史博物館は中史が晩年の4年間を過ごした京畿道果川市朱岩洞にある。 2007年には、先生が住んでいた「クワジチョダン」も復元されて建てられました。 モダンなデザインの博物館の隣に建てられた居心地の良い韓屋です。 俗世に生きる私にとって、そこは神聖な場所のようなもの。 中佐の学びを讃え、藤束父子の遺志を偲び、この夏果川への旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。 心からお勧めします。
泉 治治(いずみ じはる) 日本出身、ソクキョン大学グローバルビジネス言語学部教授
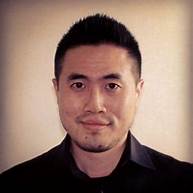
「テレビオタク。情熱的な料理のスペシャリスト。旅行の専門家。ウェブの第一人者。筋金入りのゾンビ好き。謝罪のない音楽狂信者。」

![中佐氏と藤塚氏を通じて友好的な韓日交流が続いた[이즈미 지하루 한국 블로그]](https://dimg.donga.com/wps/NEWS/IMAGE/2023/06/08/119684565.2.jpg)