こうした中、量重視から利益重視へ体質を改善した日本の建設会社の海外受注に占める中東地域の割合が1%にも満たないことが注目されている。
| ▲アル・サウードのムハンマド・ビン・サルマン皇太子は21日、日本の岸田文雄首相とテレビ会議を通じて首脳会談を行う。 |
22日、海外建設協会によると、2024年4月基準で韓国建設会社の中東向け受注額は98億ドル(約13兆ドル)で、受注総額の74.2%を占めた。
その他の地域を見ると、北米11.4%、アジア9.8%、欧州2.7%、中南米1.1%、アフリカ0.8%となっている。
最近、中東地域からの海外からの注文の割合が増加しています。 2022年に29.1%を占めていた中東からの注文は2023年には34.3%を記録し、今年は急増した。
今年4月には中東からの受注割合が1990年以来最高水準(85.9%)となった。 これはアラブ首長国連邦のバラカ原子力発電所を受注した2009年の72.7%よりも高い。
問題は、最近の中東情勢が異常であることだ。
同国の建設産業の主要市場でもあるサウジアラビアのサルマン・ビン・アブドゥルアズィズ・アル・サウド国王の健康問題が、中東情勢の突然の変動要因として浮上している。
ムハンマド・ビン・サルマン・アル・サウド皇太子も、父親のサウジアラビア国王が肺炎を患っているため、日本訪問の計画をキャンセルした。 ビン・サルマン皇太子は20日から23日まで来日する予定だったが、テレビ会議による首脳会談に変更された。
イランではエラヒム・ライシ大統領がヘリコプター墜落事故で死亡した。
もちろん、サウジアラビアの実権を握るサウジアラビアのビン・サルマン皇太子や、イラン最高権力者である最高指導者ハメネイ師(ラーバール)らが勧告したとみられる。
しかし、両国とも原則を逸脱した後継政権の準備を進めており、将来的に権力空白が生じた場合に混乱を招く可能性も排除できない。
サウジアラビアは、現在の兄弟間継承の原則から脱却し、父子継承を推進している。 イランでは、最高指導者ハメネイ師の次男モジタバ・ハメネイ氏が、世襲ではない最高指導者の次期候補とみられている。
中東地域の情勢が悪化すれば、工期の遅延は避けられないだけでなく、最悪の場合、工事代金が正しく受け取れなくなる可能性もあります。
さらに、国際情勢の不安定化により、為替レートの上昇と原油価格の高騰により、原子灰の価格が上昇しています。 また、中東地域での海外受注のマージン率がもともと低いことも収益悪化に影響を与える可能性がある。
建設業界によると、一般的に海外受注の適正マージン率は10%程度とされるが、中東地域ではこれを下回る2%程度となる。
英国の建設会社HKAは2022年に発表した報告書の中で、「中東では、高リスク、低利益の契約モデルが大半を占めている」と述べ、さらに次のように付け加えた。それは避けられないので、これは問題です。」 「それがうまく処理されなければ、必然的に紛争につながるだろう」と彼は説明した。

| ▲20日(現地時間)、イラク・バグダッドのイラン大使館前でヘリコプター墜落事故で死亡したイランのエブラヒム・ライシ大統領に追悼の意を表するイラク国民。 |
日本の建設業界がリスクの高い中東地域ではなく、アジアや北米に重点を置くよう発注構造を変更したという事実は、私たちにとっても重要な意味を持っています。
海外建設協会(OCAJI)が2024年2月に発表した「海外受注実績動向」によると、中東地域(北アフリカを含む)からの日本の海外受注額は175億円(約1524億ウォン)となった。 2022年に。 止まってしまった。 これは対外受注総額2兆0485億円(約17兆ウォン)の0.9%に相当する。
日本の建設会社が海外から工事を受注した地域のうち、アジアが54.9%(1兆1244億円)と最も高い割合を占めた。 以下、北米32.6%(6,682億円)、オセアニア4.2%(859億円)、東欧3.7%(761億円)、中南米1.9%(396億円)、アフリカと続く。 1.4%(279億円)。 欧州(88億円、0.4%)の受注高は中東に比べて低かったが、これは東欧を別に計算したためである。
しかし、もともと日本の建設会社の受注に占める中東の割合はそれほど小さくなかった。
従来、日本の建設会社はアジア地域からの受注が多かったが、2000年代半ばにはドバイの開発ブームに乗じて、中東からの受注シェアが増加した。 特に、2006 年から 2008 年にかけて、中東からの注文の割合は 20% を超えました。
2008年の金融危機の影響で、日本の建設会社が中東から受注する割合は高かったが、2009年以降は1%程度にまで低下した。
世界的な経済危機のため、ドバイ最大の国有企業であるドバイ・ワールドは2009年に債務返済の一時停止を宣言し、開発業者は建設費用を支払うことができなくなり、日本の建設会社は巨額の損失を被った。
中東で大きな損失を被った日本の建設会社は、その後、受注件数よりも収益性を確保した活動に注力することで体質改善を図った。
建設工事の需要が旺盛で経済も順調に成長しているアジアでは、日本の建設会社は建設工事の受注高を維持してきた。
さらに2014年には海外交通・都市開発事業支援区(JOIN)を設立し、収益が保証される北米への本格的な注力を開始した。 JOINは、官民パートナーシップ(PPP)型の受注を支援するために日本政府が設立した「インフラ投資機関」です。
政府支援のおかげで、2012年には海外受注全体の16.1%に過ぎなかった日本の建設会社からの北米受注は、2022年には32.6%にまで増加した。キム・ホンジュン記者
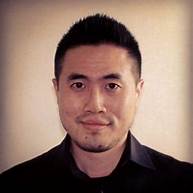
「テレビオタク。情熱的な料理のスペシャリスト。旅行の専門家。ウェブの第一人者。筋金入りのゾンビ好き。謝罪のない音楽狂信者。」


![[일본 종합상사가 눈독 들이는 미래사업은? (19)] CCUS、炭素回収から貯蔵まで脱炭素社会を推進(前編)](https://cdn.news2day.co.kr/data2/content/image/2023/02/28/.cache/512/20230228500251.jpg)
![[일본 종합상사가 눈독 들이는 미래사업은? (44)] テクノロジーで食の未来を拓くフードテック! ⑫終了](https://cdn.news2day.co.kr/data2/content/image/2024/06/13/.cache/512/20240613500137.png)


![[현장] グーグルのベンチャーキャピタル専門家は「ライン事件における日本政府と同様、韓国政府も企業を強力に支援する必要がある」と語る。](https://www.businesspost.co.kr/news/photo/202406/20240614164937_191466.png)
![[기자의눈] 少子化への特段の対策は見当たらず、まずは司令塔の強化が必要だ。](https://www.businesspost.co.kr/news/photo/202303/20230329162003_209878.jpg)